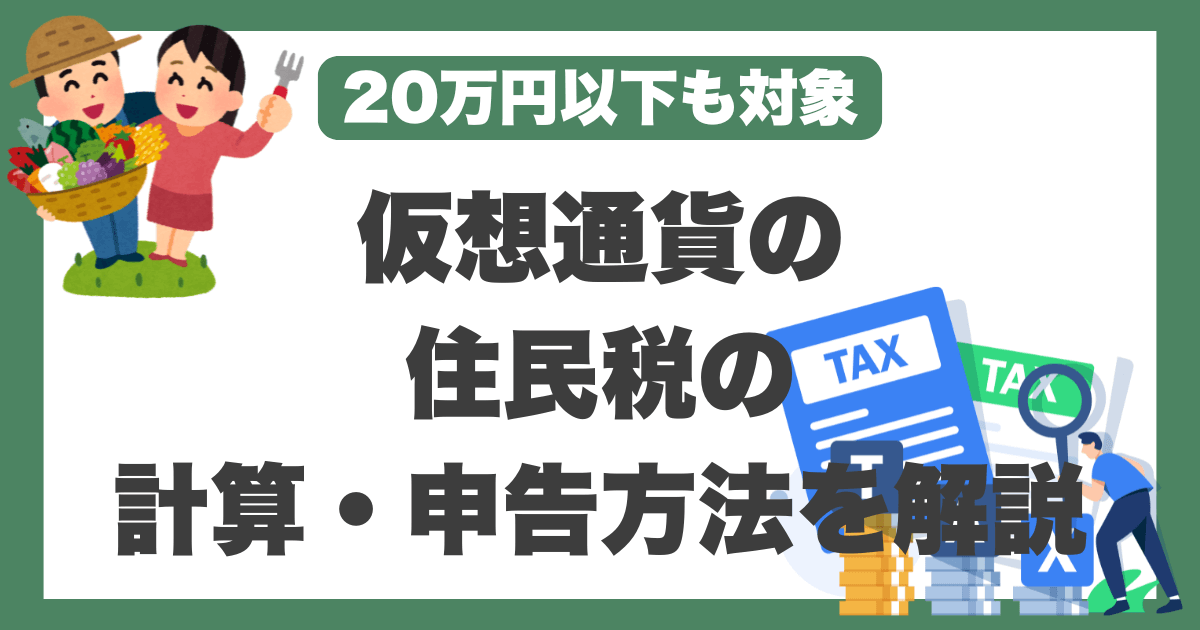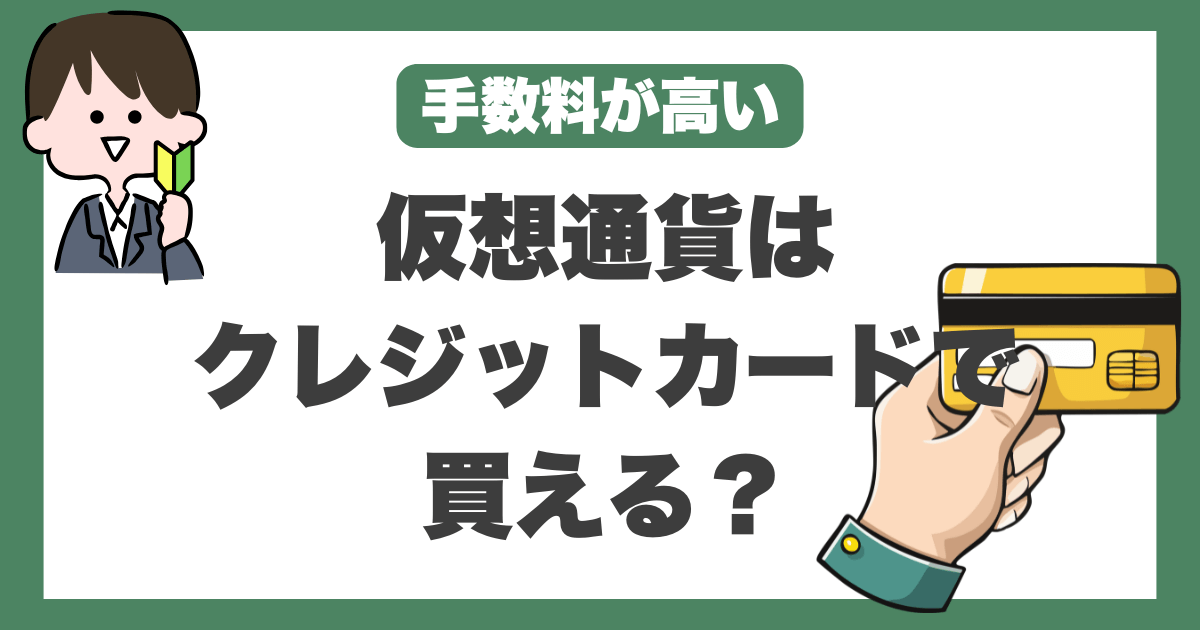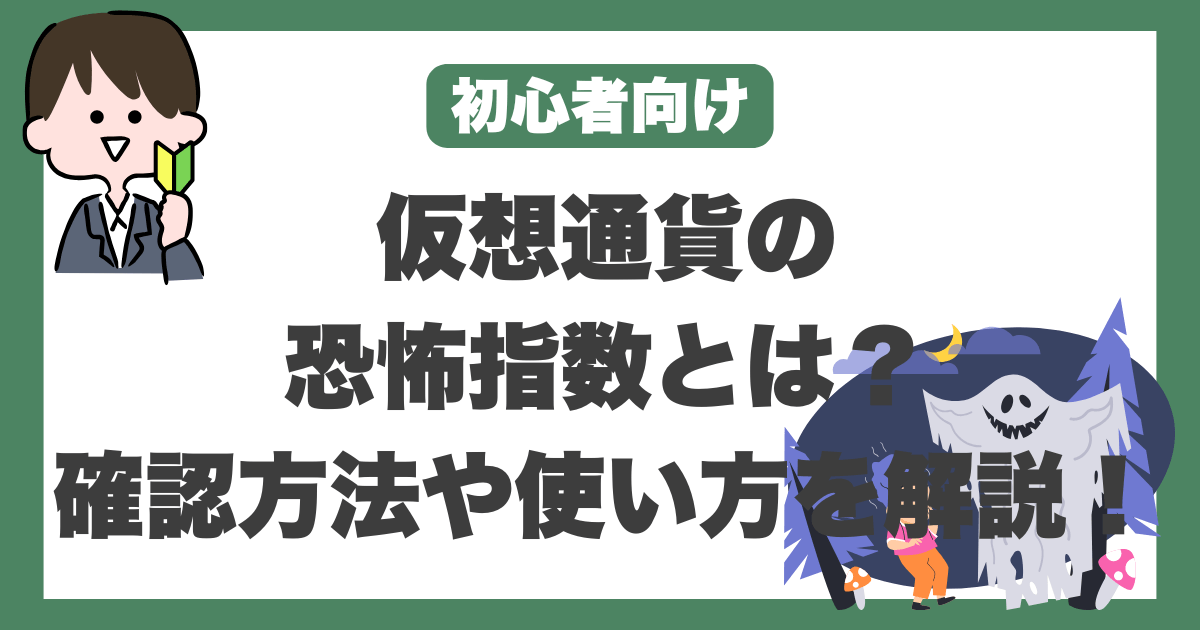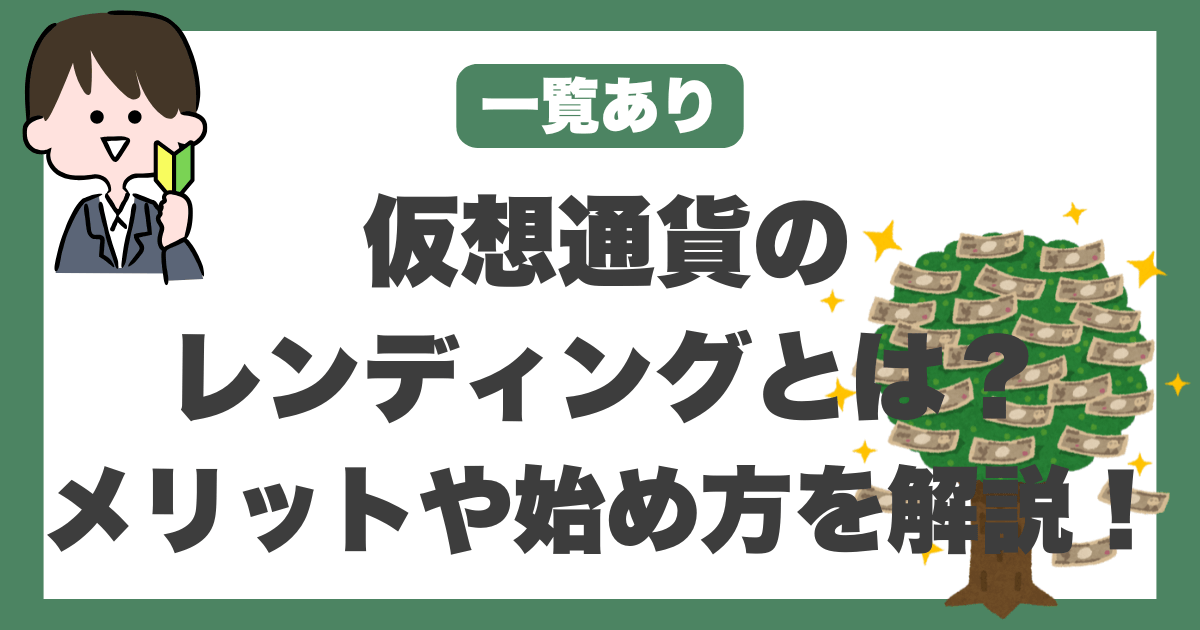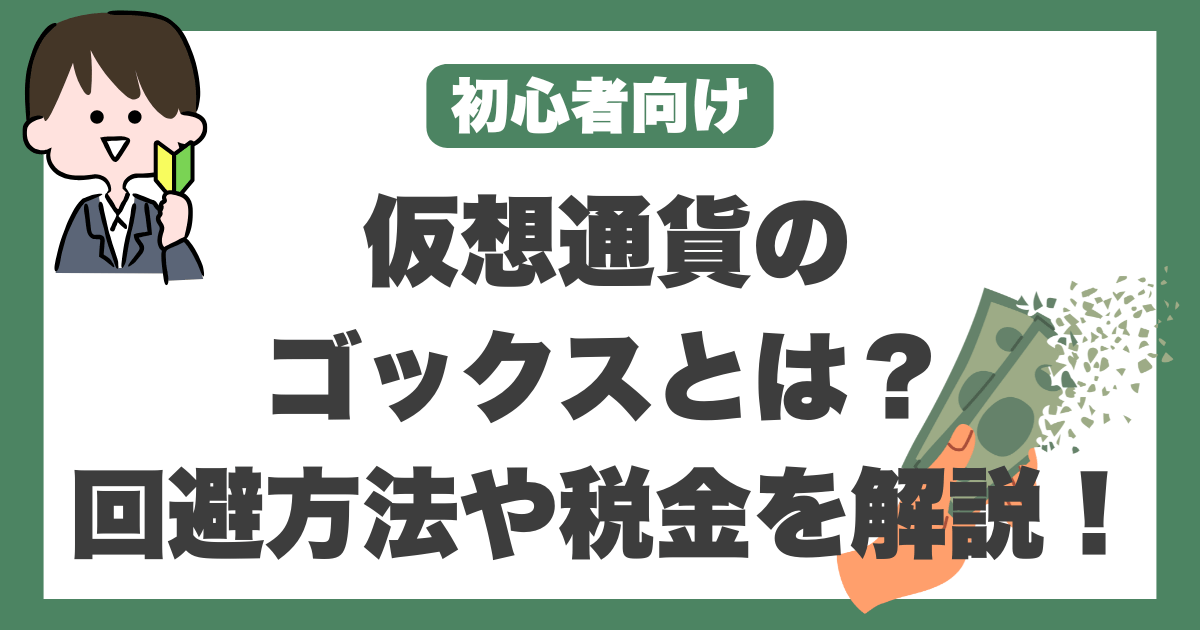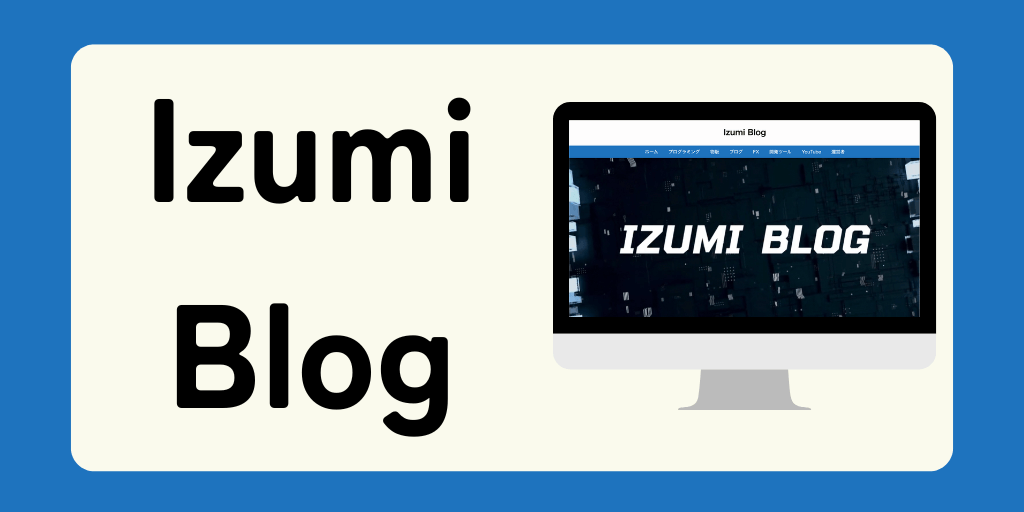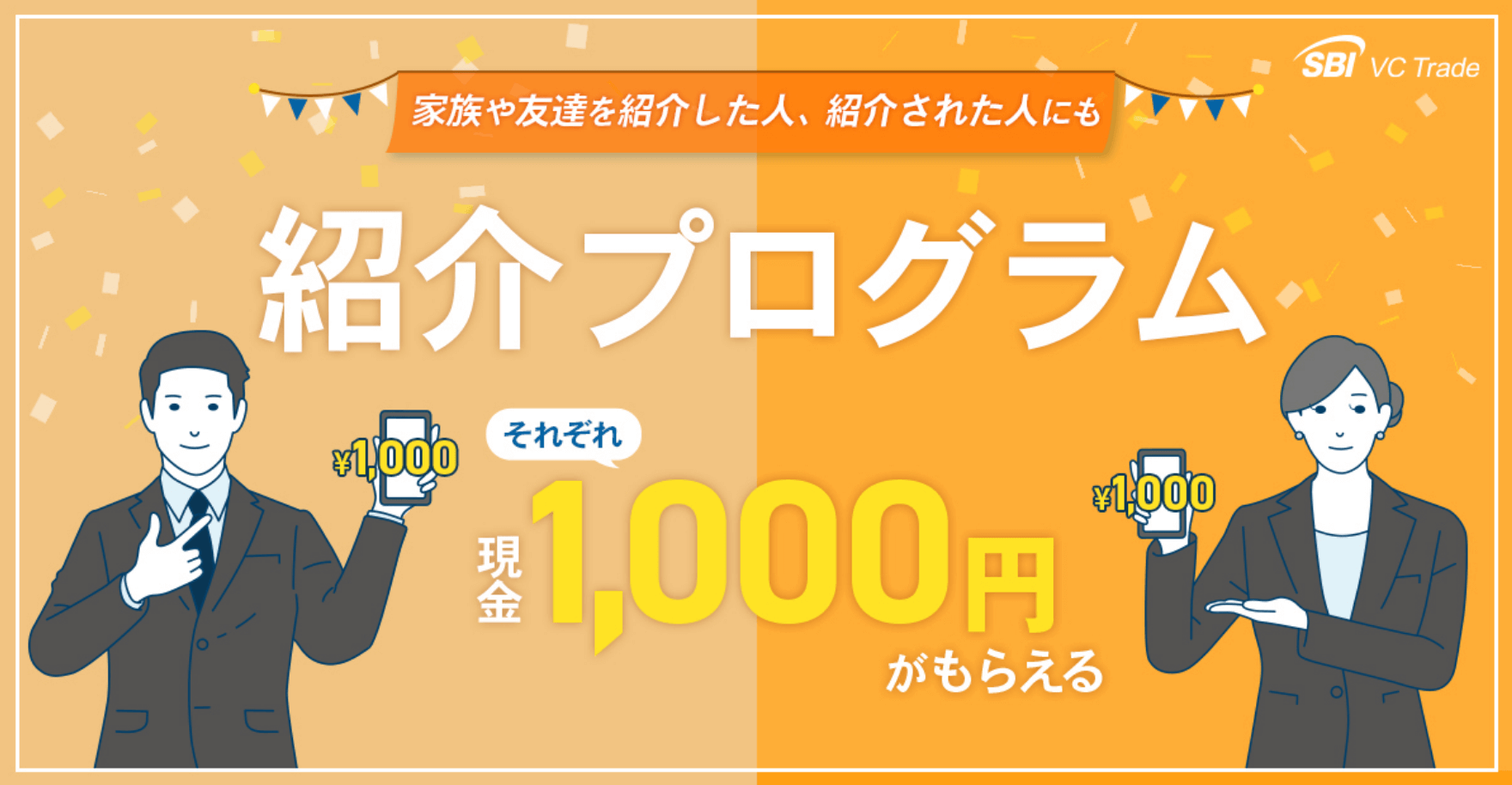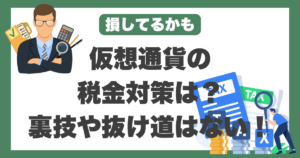【損してるかも】仮想通貨の税金対策7選!裏技や抜け道はない!
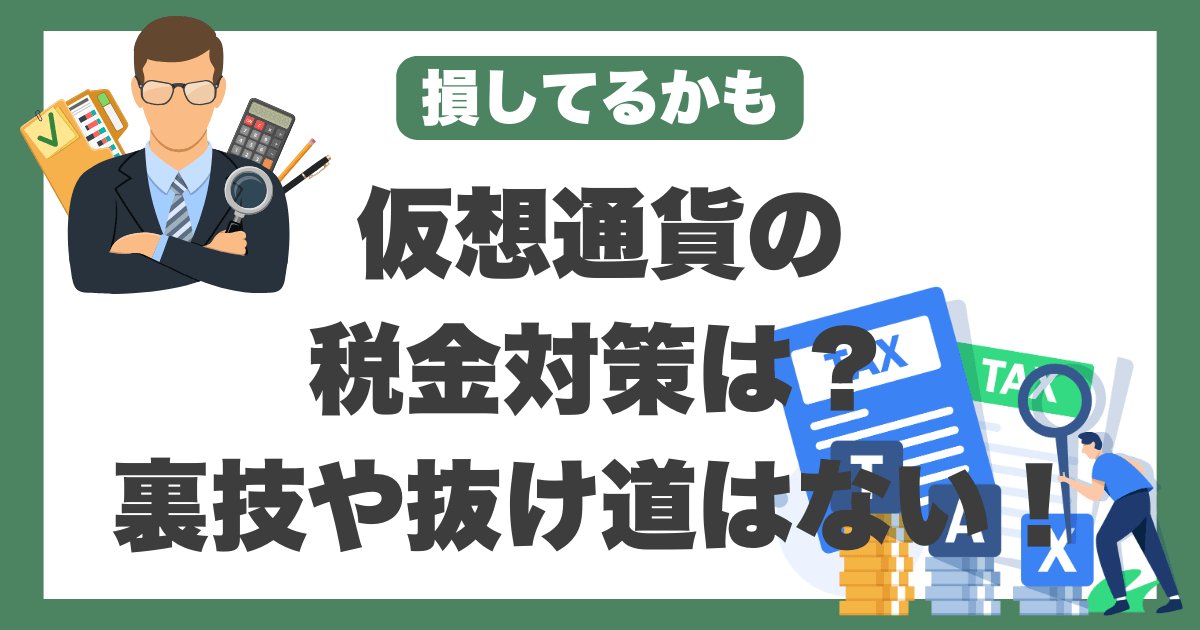
 いずみ
いずみこんな悩みを解決できる記事を書きました!
僕は仮想通貨の投資歴5年で100万円以上を運用しています。
「仮想通貨の税金が高いから税金対策したい!」とお考えではありませんか?
仮想通貨で利益が出た場合、残念ながら税金を払わなければいけません。
できる限り税金対策をして、なるべく手元に残るお金を増やしたいですよね?



僕も利益が出た時にたくさん税金を取られました…
税金許すまじ…
ということで、本記事では「仮想通貨の税金対策」について解説していきます。


本記事を読めば、仮想通貨の税金対策について完璧に理解できるので早速見ていきましょう!



すぐ読み終わるので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
| 【当サイト】おすすめ国内取引所3選 | |||
|---|---|---|---|
| 国内取引所 | 評価 | ポイント | 公式サイト |
BITPOINT | 4.5 | 迷ったらココ! 積立が完全無料、ステーキングの利率も◎ | 公式 |
bitbank | 4.3 | アルトコインの取扱数が豊富。 | 公式 |
コインチェック | 4.1 | 4年連続アプリダウンロード数No.1。 | 公式 |
※評価の判断基準については、編集ポリシーの「国内取引所に関する判断基準」を参照。
- キャンペーン情報


- BITPOINT
- 仮想通貨を合計1,000円以上購入
※開催期間は「2026年2月2日」まで。
※BITPOINTのキャンペーンは「【超お得】BITPOINT(ビットポイント)の紹介コードは?キャンペーン情報も!」を参照。
\ 口座開設&購入で2,000円貰える /
本サイトでは、金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」で認可を受けた仮想通貨取引所の利用を推奨しています。また、本サイトの「仮想通貨」は「暗号資産」のことを指します。
仮想通貨に関する注意事項は、金融庁による「暗号資産の利用者のみなさまへ」をご覧ください。
本記事は投資収益の保証、または特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資や契約の決定はご自身でご判断ください。
【悲報】仮想通貨は雑所得で最大税率45%
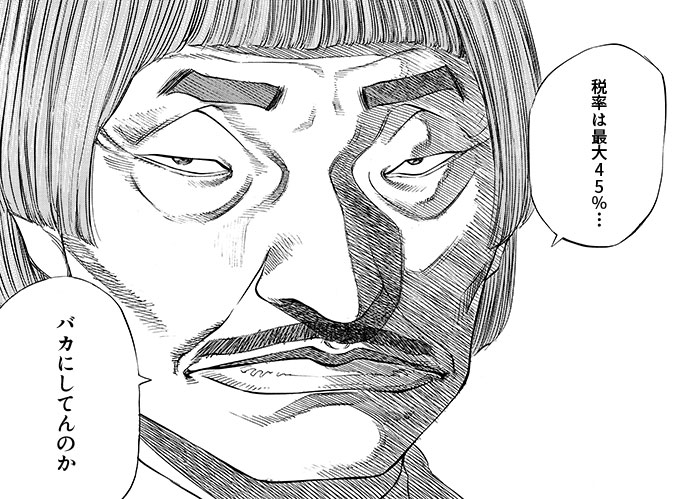
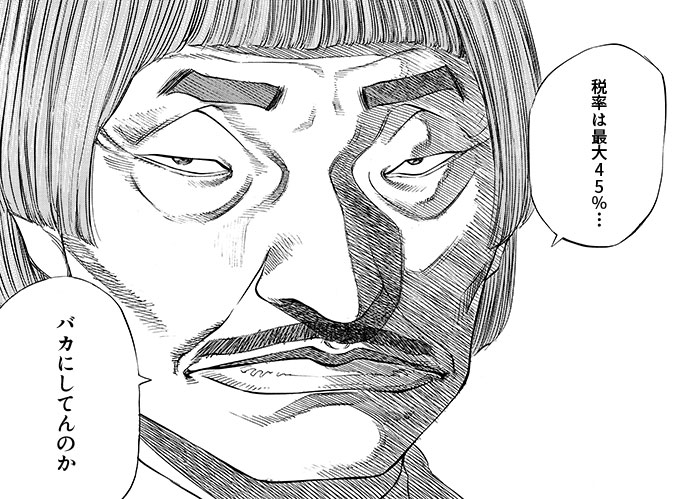
仮想通貨の所得は原則として雑所得に分類されます。
雑所得の税率は最大45%で、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる累進課税です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000〜1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000〜3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000〜6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000〜8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000〜17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000〜39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円まで | 45% | 4,796,000円 |



簡単に言うと、税金をガッツリ取られるってことです(笑)
ということで、なるべく税金を抑えるための対策方法を解説しますね♪
【損してるかも】仮想通貨の税金対策7選


仮想通貨の税金対策はいくつかありますが、それぞれに難易度を付けて解説します。



ちなみに、巷で言われている税金対策で現実的ではない方法があるので、その辺りも細かくお伝えしますね。
事業所得にする


仮想通貨は雑所得に該当するため事業所得ではありません。
事業所得であれば他の所得と損益通算できたり、損失による控除を3年間繰り越すことができたりとメリットを享受できます。
ただし、仮想通貨の所得を事業所得にするには最低でも仮想通貨の所得が年間300万円を超えていないと厳しいと言われています。



仮想通貨の取引は本業の片手間で行うものとされているため、事業としては認められにくい傾向にあります。
基本的には事業所得にならないので注意してください。
経費を計上する
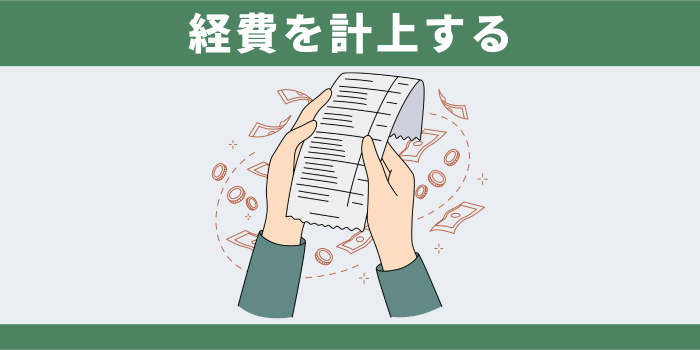
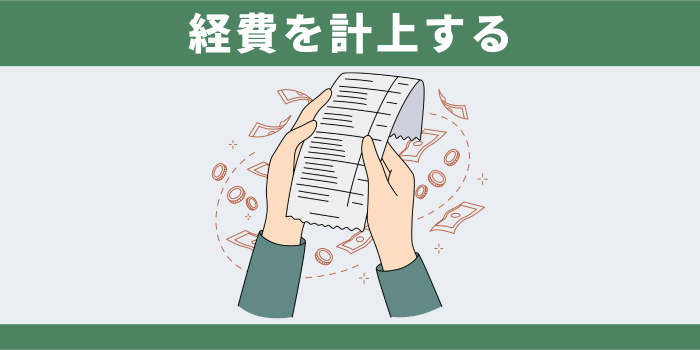
仮想通貨の取引に関する必要経費は、経費として計上可能です。
例えば、取引所の手数料や関連書籍、セミナー費用などは経費として申告できます。
経費をしっかり計上することで税負担を減らせるので、結果的に手元に残るお金が増えますよ。



経費は忘れないようにメモしておきましょう。
節税して浮いたお金は利益みたいなもんですよ。
売却しない
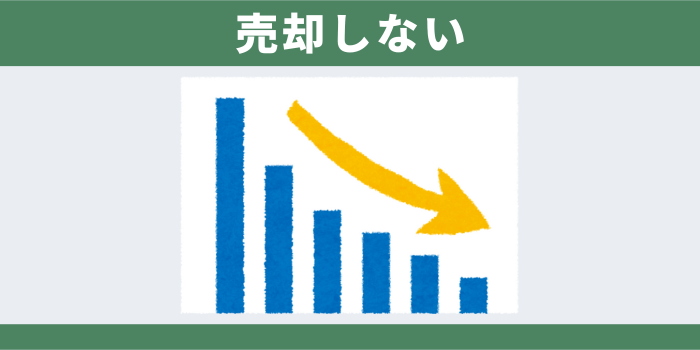
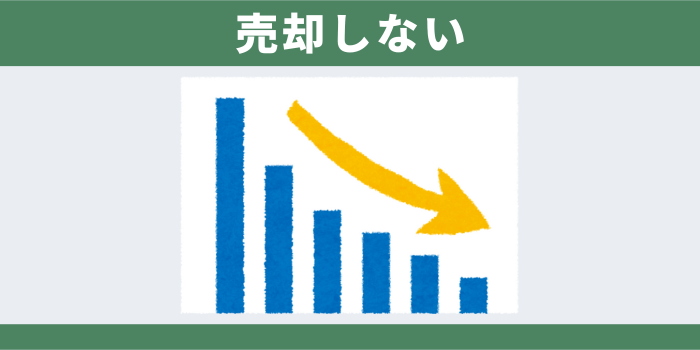
仮想通貨を売却せずに保有している間は利益が確定しないため、税金を支払う必要はありません。
税金が発生するのは売却時なので、売却を遅らせることで税金の支払いを先延ばしにできます。
ただし、利益を出すのが先決なので、税金の支払いばかりに気を取られないようにしましょう。



まずは稼ぐのが先です。
税金を考慮しすぎた結果、売却タイミングを逸するのは本末転倒なので気をつけてくださいね。
損益通算する
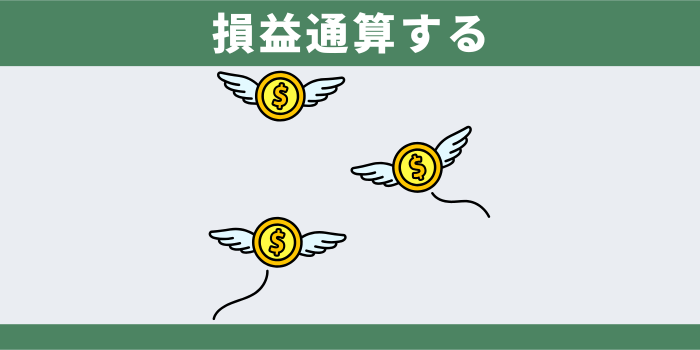
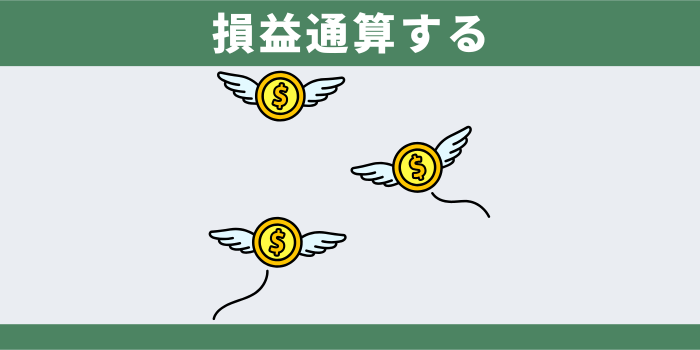
仮想通貨の取引で損失が発生した場合、他の所得と損益通算を行うことで税金を減らせます。
例えば、株式やFXで得た利益と損失を合算することで、税金の支払いを軽減できます。
損益通算を上手に活用すれば、年間の税負担を大きく削減できますよ。
年間利益を20万円以下にする


仮想通貨は年間20万円を超える利益に所得税がかかるため、利益を年間20万円以下にすれば所得税はかかりません。
例えば、仮想通貨で40万円の利益が出ている場合、利益確定すると2万円(利益の5%)の所得税がかかります。
ただし、本年度に20万円分の利益を確定し、翌年に残りの20万円を利益確定すれば、所得税を支払う必要はありません。



利益確定のタイミングが年末に近い場合は、年を跨ぐ形で利益確定すればお得といった感じですね。
なかなか狙って実行するのは難しいですが、知っておいて損はありません。
開業する
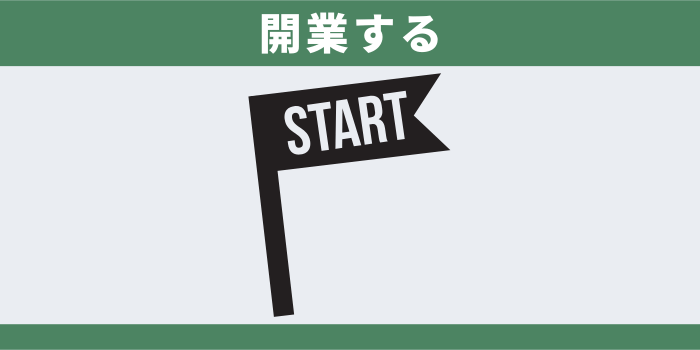
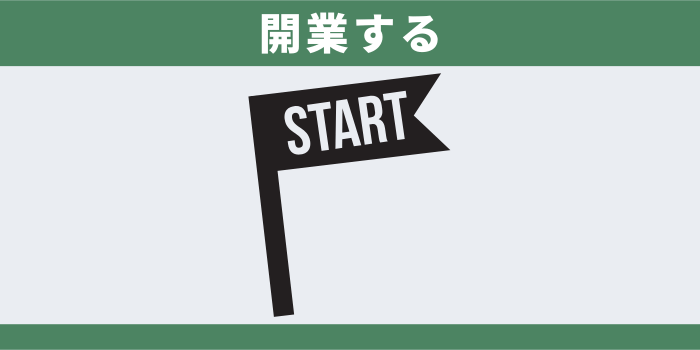
仮想通貨の取引を事業として開業し、事業所得として申告すれば経費を計上しやすくなります。
ただし、「事業所得にする」でもお伝えしたとおり、仮想通貨を事業にするのは一般人にはほぼ不可能です。
ですので、事業として申告できるほどの利益を出している場合のみ、開業するのがおすすめです。



まあ無理なものは無理なので(笑)
法人化する
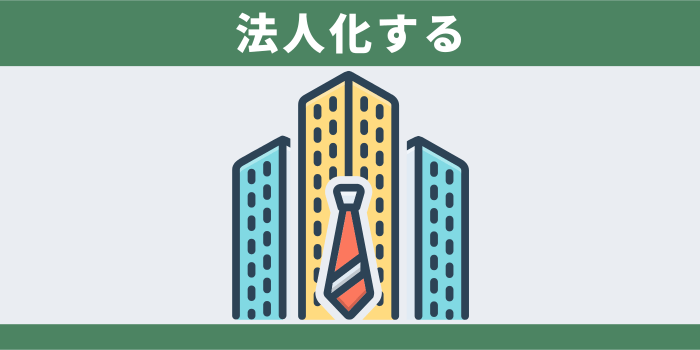
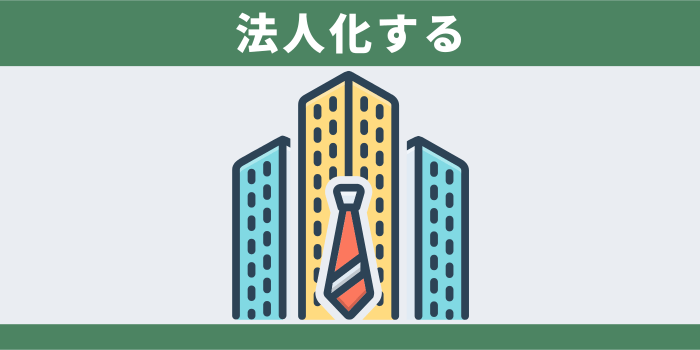
仮想通貨の利益が多い場合、法人を設立することで法人税が適用されるので税率を下げられます。
雑所得の最高税率45%と比較して、法人税の最高税率は25.5%なので大幅に税負担を軽減できます。
ただし、法人設立自体にコストがかかるので、仮想通貨の税金のためだけに法人を設立するのは現実的ではありません。



法人設立は約30万円かかりますし、利益がない年度も法人住民税の支払い義務があるので7万円がかかります。
また、法人設立は税理士に依頼するのが一般的なので、顧問料も別途かかります。
【厳選】仮想通貨の損益計算ツール2選
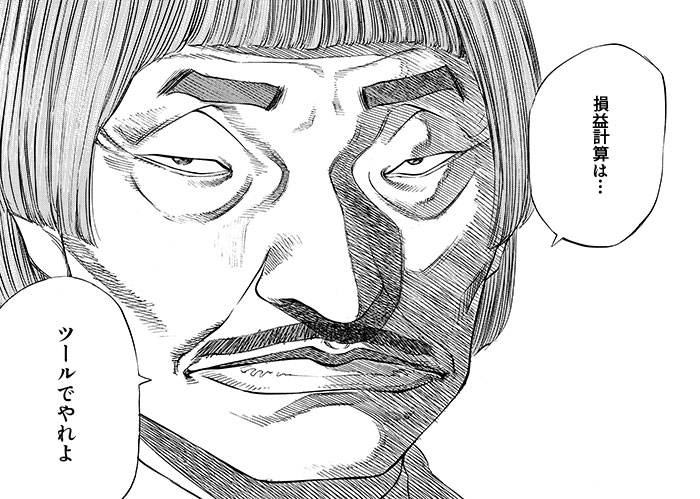
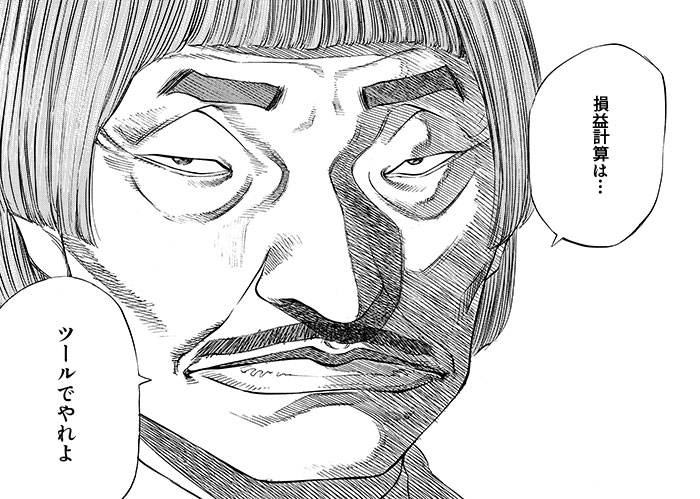
仮想通貨の損益計算は損益計算ツールを使いましょう。
取引所の取引データをアップロードするだけで自動で損益を計算してくれるので時短になりますよ。



僕は「Cryptact
めちゃ便利なのでぜひ使ってくださいね。
損益計算サービス利用者No.1「Cryptact

- 損益計算サービスにおける利用者数No.1(2019年7月調べ)
- 対応取引所数、対応コイン数、対応取引種類数で総合1位
- 取引履歴をアップロードするだけで、最短10秒で仮想通貨の損益計算ができる
Cryptact
対応取引所数、対応コイン数、対応取引種類数も総合1位なので安心して使えますよ♪
税理士事務所導入数100超え「Gtax

- 税理士事務所の導入数は100以上
- 対応通貨数は約15,000以上
- 対応取引所は約70以上
- 取引件数100件まで無料
Gtax
対応取引所は約70以上で、DeFiにも対応しています。
【厳選】仮想通貨のおすすめ取引所3選
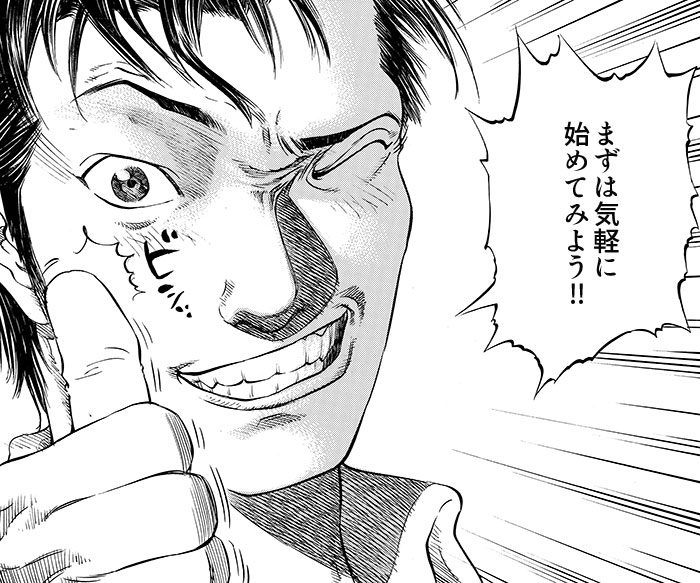
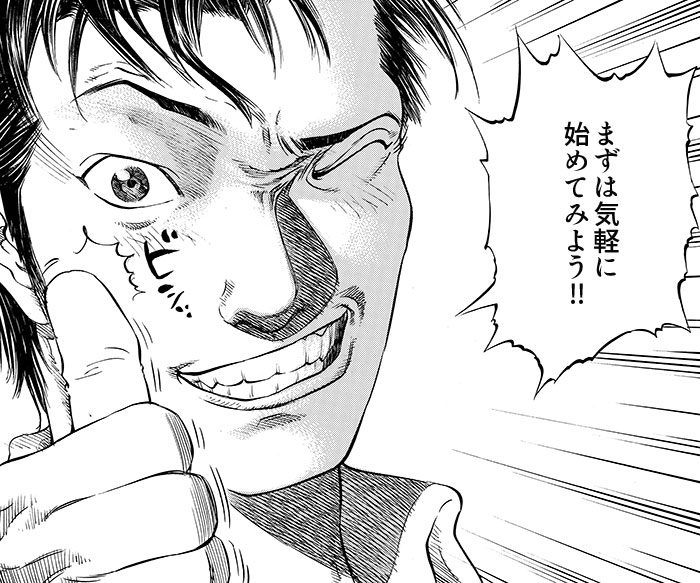
仮想通貨を始めるには国内取引所の口座開設が必要です。
一つの取引所に絞るとリスクが大きいので、必ず複数の口座を開設して資金を分散させましょう。



今回は、セキュリティ対策が万全で国内ユーザー数の多い取引所をご紹介します。
もちろん、僕もすべて口座開設しています!
※評価の判断基準については、編集ポリシーの「国内取引所に関する判断基準」を参照。
【迷ったらココ!】初めてでも安心「BITPOINT

- SBIホールディングスのグループ会社
- 圧倒的な手数料の安さ
- 取扱通貨数は30通貨
- 積立手数料が完全無料、ステーキングも可能
※1 口座開設手順は「【保存版】BITPOINT(ビットポイント)とは?珍しい通貨が豊富!」を参照。
※2 キャンペーン情報は「【超お得】BITPOINT(ビットポイント)の紹介コードは?キャンペーン情報も!」を参照。
SBIホールディングスのグループ会社なので信頼性は抜群です。
各種手数料が無料で、ステーキングも可能なので初心者の人にもおすすめです。
取扱通貨数なら「bitbank」
- アルトコインの取扱数が豊富
- 1円未満から購入できる
- 60種のテクニカル分析を利用できるリアルタイムチャート
※1 口座開設手順は「【手数料安】bitbankとは?アルトコインの購入におすすめ!」を参照。
※2 キャンペーン情報は「【バチクソお得】bitbank(ビットバンク)のキャンペーン情報!紹介コードは?」を参照。
bitbankはアルトコインの取扱数が豊富な取引所です。
1円未満から購入できるので、初心者にもおすすめですよ。
国内ユーザー数No.1「コインチェック

- 4年連続アプリダウンロード数No.1(※1)
- 最低500円から購入できる
- マネックスグループ傘下の徹底したセキュリティ体制
※1 国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年〜2022年、データ協力:AppTweak
※2 口座開設手順は「【初心者向け】Coincheckとは?国内ユーザー数No.1!」を参照。
※3 キャンペーン情報は「【バチクソお得】Coincheck(コインチェック)の紹介コードで特典を貰う方法」を参照。
コインチェック
マネックスグループなのでセキュリティ体制も万全ですよ。
よくある質問
仮想通貨の最大税率はいくつですか?
仮想通貨の税金対策は何がありますか?
仮想通貨の税金対策には「経費を計上する」や「年間利益を20万円以下にする」などがあります。
仮想通貨のデビットカードは税金対策になりますか?
デビットカードでの税金対策はできません。
仮想通貨のデビットカードで支払った場合、仮想通貨を法定通貨に換えて支払ったと見なされるので、支払いした時点で損益が確定します。
損益確定時に利益が出ていた場合は課税対象となるため注意が必要です。
まとめ
今回は、仮想通貨の税金対策について解説しました。
以下が本記事のまとめになります。
税金対策をしっかりして、手元に残るお金を増やしましょうね。



最後までお読みいただき、ありがとうございました!
| 【当サイト】おすすめ国内取引所3選 | |||
|---|---|---|---|
| 国内取引所 | 評価 | ポイント | 公式サイト |
BITPOINT | 4.5 | 迷ったらココ! 積立が完全無料、ステーキングの利率も◎ | 公式 |
bitbank | 4.3 | アルトコインの取扱数が豊富。 | 公式 |
コインチェック | 4.1 | 4年連続アプリダウンロード数No.1。 | 公式 |
※評価の判断基準については、編集ポリシーの「国内取引所に関する判断基準」を参照。
- キャンペーン情報


- BITPOINT
- 仮想通貨を合計1,000円以上購入
※開催期間は「2026年2月2日」まで。
※BITPOINTのキャンペーンは「【超お得】BITPOINT(ビットポイント)の紹介コードは?キャンペーン情報も!」を参照。
\ 口座開設&購入で2,000円貰える /
- 仮想通貨一覧
| ティッカーシンボル | 名称 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ADA | Cardano(カルダノ) | 4.6 | 詳細 |
| AIMX | Aimedis(アイメディス) | 2.2 | 詳細 |
| AIOZ | AIOZ Network(エイオズ ネットワーク) | 3.4 | 詳細 |
| APE | ApeCoin(エイプコイン) | 3.2 | 詳細 |
| ARB | Arbitrum(アービトラム) | 4.0 | 詳細 |
| ASTR | Astar(アスター) | 3.4 | 詳細 |
| AVAX | Avalanche(アバランチ) | 4.6 | 詳細 |
| AXS | Axie Infinity(アクシーインフィニティ) | 2.6 | 詳細 |
| AZERO | Aleph Zero(アレフ ゼロ) | 2.4 | 詳細 |
| BCH | Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ) | 3.0 | 詳細 |
| BNB | BinanceCoin(バイナンスコイン) | 4.4 | 詳細 |
| BONK | Bonk(ボンク) | 2.8 | 詳細 |
| BTC | Bitcoin(ビットコイン) | 4.8 | 詳細 |
| CHNG | Chainge Finance(チェインジ ファイナンス) | 2.6 | 詳細 |
| CHZ | Chiliz(チリーズ) | 3.2 | 詳細 |
| DOGE | Dogecoin(ドージコイン) | 3.6 | 詳細 |
| DOT | Polkadot(ポルカドット) | 4.6 | 詳細 |
| ETH | Ethereum(イーサリアム) | 4.8 | 詳細 |
| GALA | Gala Games(ガラ ゲームズ) | 3.4 | 詳細 |
| GRT | The Graph(ザ・グラフ) | 4.0 | 詳細 |
| HBAR | Hedera(へデラ) | 4.2 | 詳細 |
| HYPE | Hyperliquid(ハイパーリキッド) | 3.8 | 詳細 |
※「評価」は各記事に詳細を記載しています。